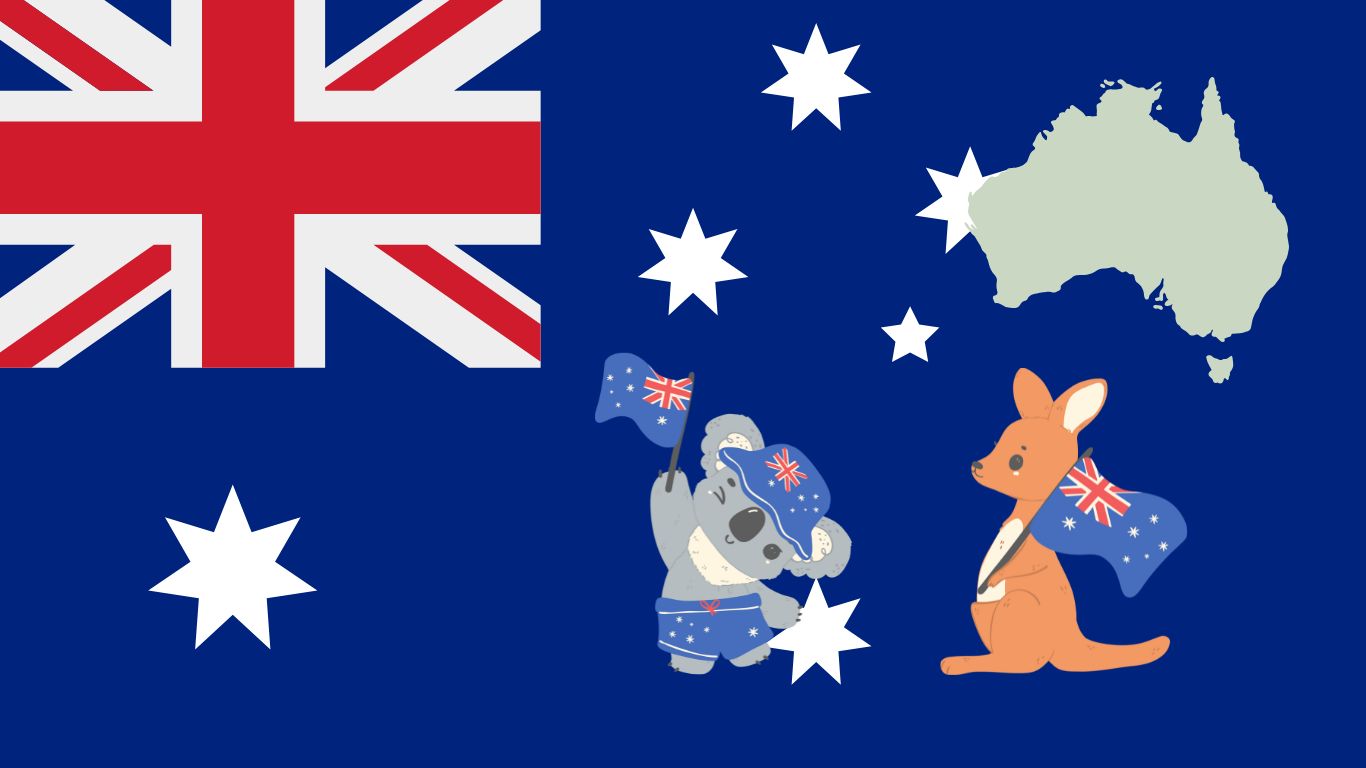上席顧問津田克彦先生のブログ
新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(6) 2025.7.25 「海外引率体験記(第5回)」
2025/07/25 公開
2025/08/06 update
今年は関西の梅雨明けが早く、6月下旬から真夏の気温が続いています。今年の夏は長くなりそうです。夏と言えばお祭りのシーズンです。大阪の天神祭り、京都の祇園祭などのニュースがテレビで放映されると「本格的な夏が来た!」と感じます。私の勤務していた学校は大川(淀川の旧流路)の近くにあり、天神祭りの船渡御や花火が間近で見られました。学院の周年事業の一環として学院船も参加させていただいた時期があり、私も何度か乗船してお祭りを味わったことが良い思い出です。
私が若手だった頃(1980年代)の校長が「環太平洋構想」を打ち立てました。今でこそ「国際化」「グローバル化」などの言葉が頻繁に聞かれるようになり小学校でも当たり前のように国際(英語を中心とした)教育が取り入れられていますが、当時はまだまだ国際教育が先の見えない時代だったので、その先見性と実行力は今更ながら驚くものがあります。 「環太平洋構想」とは太平洋を囲む国々の小学校と交流をしていこうというものです。以前から交流のある「ハワイ」に加えて「オーストラリア」「韓国」「台湾」「カナダ」の5か国です。
「台湾編」
今回は台湾との交流をお話ししたいと思います。台湾は台北市内になる私立の小中学校と交流することになりました。第1回目の訪問は私の担当していた5年生の児童10人と共に3泊4日の日程で訪れました。到着後すぐに小学校で歓迎式典が行われました。この訪問はハワイのようなホームステイではなく、学校が所有する郊外の立派な宿泊施設で台湾の5年生の児童30名と合同キャンプという形で3泊を過ごしました。初回ということもありいろいろなイベントを準備していただき、なかなかのハードスケジュールでした。我々日本の教師団には前日の夜に予定が渡されるのですが、すべてのイベントが台湾対日本の対抗戦形式で両校の校長が採点するというもの、我々も負けるわけにはいきません。例えば各学校で20分間の寸劇の発表会なんて言うものもありました。夜の間に先生方で簡単な台本や小道具なども制作したので就寝時刻が午前3時を回っていました。我々は日本の昔話を題材にした紙人形劇を披露し高い評価を得られたのでホッとしました。それ以外にもダンスパフォーマンスもあり、我々は昔からある学校の音頭を浴衣(国際交流にはいつも浴衣を持参させています)を着て披露しました。釣り堀(普段はプール)での魚釣り大会や広場でのミニ運動会も対抗戦で子どもたちより、両校の先生方が必死に応援したり勝敗に一喜一憂したことを覚えています。対抗戦だけではなく両校の児童がクループをつくり動物園に行ったりバーベキューをして楽しく過ごしました。子どもたちのコミュニケーション方法をみているとそれぞれの母国語にジェスチャーをまじえて意思疎通を図っていましたが、お互いの片言の英語(私の学校でも1年生から英語の授業がありましたが当時は台湾の子どもたちの方が英語力が優れていました)が通じることを知り、海外において英語の必要性を感じて帰国し、その後英語の勉強に力を入れた子どももいました。
この台湾訪問で引率したのは私の担当している子どもたちでした。学校での成績が優秀な子もいれば少し苦労している子をいました。真面目な子もいればヤンチャな子もいました。学校生活を離れ、海外での生活や違う国の子どもたちとの交流で活躍する子は必ずしも成績優秀で真面目な子ではなく、少しヤンチャで積極性(意欲)のある子だということが分かりました。グローバル化が急速に進む現代の日本では、成績優秀や真面目さはもちろん大切ですが、それだけでなく少々ヤンチャでも積極性のある意欲のある子どもたちが活躍する時代だと思います。
この年の後半には台湾の小学生が日本を訪問しました。学校で歓迎式典をしたり、教室に入って一緒に授業を受けたり、京都の太秦映画村を見学したりして楽しく過ごしていました。この交流はその後3年続きましたが、ハワイやオーストラリアのようにホームステイがあるわけでもなく観光旅行に近いということで児童の作品(習字や絵画など)交換や教職員の交流が主となり児童の相互訪問は終わりました。訪問日数も実施した年数も短い国際交流でしたが、現地の下見を兼ねた事前の打ち合わせから担当した私にとって中身の濃い思い出深い台湾訪問でした。
私が若手だった頃(1980年代)の校長が「環太平洋構想」を打ち立てました。今でこそ「国際化」「グローバル化」などの言葉が頻繁に聞かれるようになり小学校でも当たり前のように国際(英語を中心とした)教育が取り入れられていますが、当時はまだまだ国際教育が先の見えない時代だったので、その先見性と実行力は今更ながら驚くものがあります。 「環太平洋構想」とは太平洋を囲む国々の小学校と交流をしていこうというものです。以前から交流のある「ハワイ」に加えて「オーストラリア」「韓国」「台湾」「カナダ」の5か国です。
「台湾編」
今回は台湾との交流をお話ししたいと思います。台湾は台北市内になる私立の小中学校と交流することになりました。第1回目の訪問は私の担当していた5年生の児童10人と共に3泊4日の日程で訪れました。到着後すぐに小学校で歓迎式典が行われました。この訪問はハワイのようなホームステイではなく、学校が所有する郊外の立派な宿泊施設で台湾の5年生の児童30名と合同キャンプという形で3泊を過ごしました。初回ということもありいろいろなイベントを準備していただき、なかなかのハードスケジュールでした。我々日本の教師団には前日の夜に予定が渡されるのですが、すべてのイベントが台湾対日本の対抗戦形式で両校の校長が採点するというもの、我々も負けるわけにはいきません。例えば各学校で20分間の寸劇の発表会なんて言うものもありました。夜の間に先生方で簡単な台本や小道具なども制作したので就寝時刻が午前3時を回っていました。我々は日本の昔話を題材にした紙人形劇を披露し高い評価を得られたのでホッとしました。それ以外にもダンスパフォーマンスもあり、我々は昔からある学校の音頭を浴衣(国際交流にはいつも浴衣を持参させています)を着て披露しました。釣り堀(普段はプール)での魚釣り大会や広場でのミニ運動会も対抗戦で子どもたちより、両校の先生方が必死に応援したり勝敗に一喜一憂したことを覚えています。対抗戦だけではなく両校の児童がクループをつくり動物園に行ったりバーベキューをして楽しく過ごしました。子どもたちのコミュニケーション方法をみているとそれぞれの母国語にジェスチャーをまじえて意思疎通を図っていましたが、お互いの片言の英語(私の学校でも1年生から英語の授業がありましたが当時は台湾の子どもたちの方が英語力が優れていました)が通じることを知り、海外において英語の必要性を感じて帰国し、その後英語の勉強に力を入れた子どももいました。
この台湾訪問で引率したのは私の担当している子どもたちでした。学校での成績が優秀な子もいれば少し苦労している子をいました。真面目な子もいればヤンチャな子もいました。学校生活を離れ、海外での生活や違う国の子どもたちとの交流で活躍する子は必ずしも成績優秀で真面目な子ではなく、少しヤンチャで積極性(意欲)のある子だということが分かりました。グローバル化が急速に進む現代の日本では、成績優秀や真面目さはもちろん大切ですが、それだけでなく少々ヤンチャでも積極性のある意欲のある子どもたちが活躍する時代だと思います。
この年の後半には台湾の小学生が日本を訪問しました。学校で歓迎式典をしたり、教室に入って一緒に授業を受けたり、京都の太秦映画村を見学したりして楽しく過ごしていました。この交流はその後3年続きましたが、ハワイやオーストラリアのようにホームステイがあるわけでもなく観光旅行に近いということで児童の作品(習字や絵画など)交換や教職員の交流が主となり児童の相互訪問は終わりました。訪問日数も実施した年数も短い国際交流でしたが、現地の下見を兼ねた事前の打ち合わせから担当した私にとって中身の濃い思い出深い台湾訪問でした。
The following two tabs change content below.


上席顧問 津田克彦
元私立小学校校長、元大阪府私立小学校連合会会長。
プラチナム学習会では保護者相談、進学指導、及び、「小学校受験対策集団コース」を担当。元私立小学校校長の長年の経験を活かした、噂に左右されない本質的な指導で万全の準備を進めます。特に小学校入学後に後伸びできる子ども達の指導に努めています。
最新記事 by 上席顧問 津田克彦 (全て見る)
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(8) 2025.11.10 - 2025/11/10
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(7) 2025.9.30 - 2025/09/30
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(6) 2025.7.25 「海外引率体験記(第5回)」 - 2025/07/25