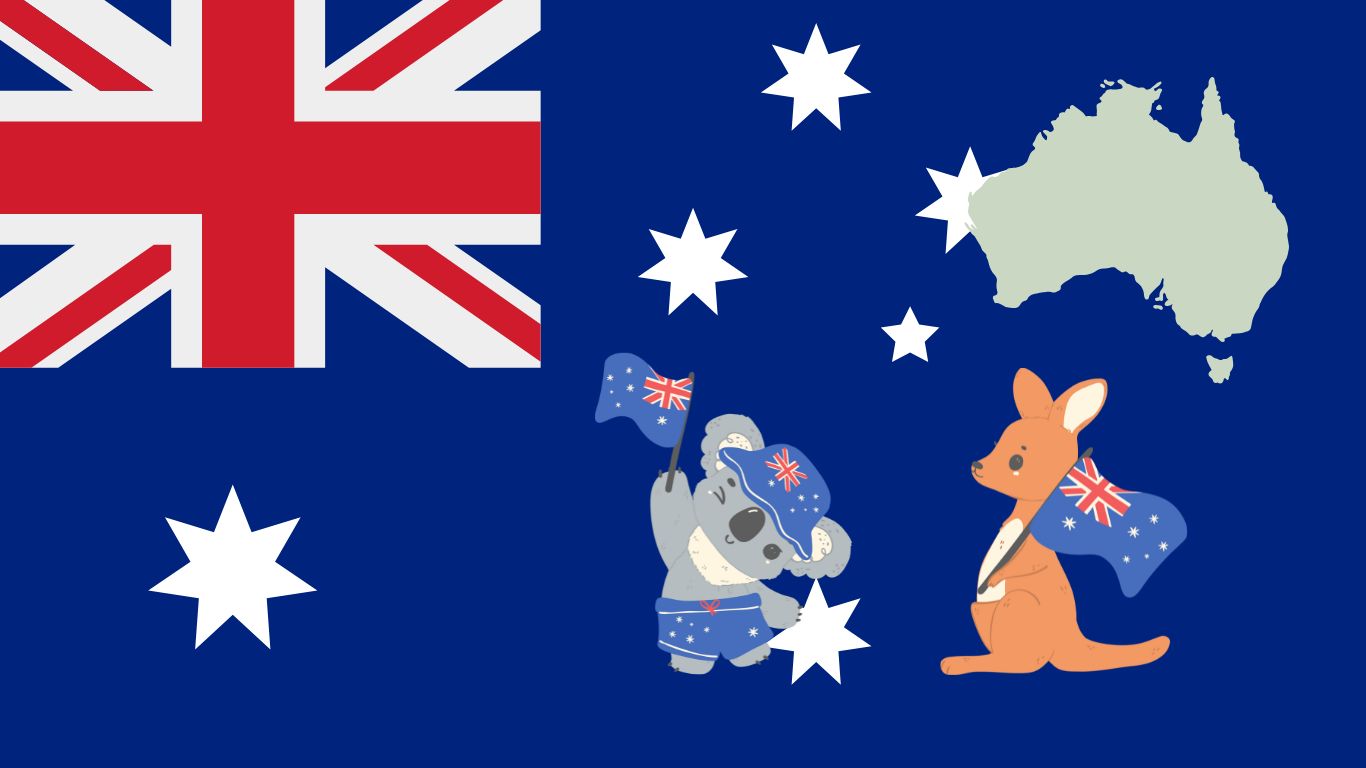上席顧問津田克彦先生のブログ
新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(7) 2025.9.30
2025/09/30 公開
2025/10/04 update
「海外引率体験記(第6回)」
「暑い!」「暑い!」と言い続けた今年の夏も9月下旬に入り秋を感じるようになってきました。今年の夏は早くから始まり遅くまで続く長い夏でした。私は今年はじめて日傘を購入しました。いままで日傘は女性が使うものという認識で男性の自分が使うなんて考えもしませんでしたが使ってみて帽子よりはるかに涼しく快適でした。今年は男性でも日傘を使う人が増えていると聞きます。また中高生はもちろん通学に日傘を使う小学生も見かけました。今後、数年前から流行りだしたハンディファンのようにかわいいデザインや新しい機能を備えた日傘が流行るかもしれませんね。
さて、海外引率体験記も「ハワイ編」「台湾編」と続きましたが今回はオーストラリア
をご紹介します。
「オーストラリア編」
私の勤務していた小学校とオーストラリアのブリスベンにある小学校の交流が始まったのは1995年(平成7年)からです。ハワイや台湾と同じく「環太平洋計画」の一環として早くから準備を進め、初めに先生方の交流から始めました。ハワイ(約6.5時間)や台湾(3.5時間)にくらべてフライト時間が長い(約9時間)ので心配しましたが時差がほとんどない(1時間)ので実施可能と判断しました。オーストラリア訪問でもメインはホームステイです。ハワイと違いオーストラリアのご家庭は日本語を話せる方は皆無に近く、さらに1家庭に1人での訪問(ハワイは2人一組)で少しハードルが高くなります。それでも毎年たくさんの希望者がいて子どもたちの勇気に感心させられたものです。行事はハワイと同じように学校訪問や歓迎行事、ホームステイなどで充実した日々を過ごします。オーストラリアのホームステイを経験した子どもたちは他の訪問先にくらべても英語や異国文化への関心が高くなって帰ってきたように感じました。ブリスベンはビジネス街なので派手な観光地はありませんが、豊かな自然と動物(コアラなど)との触れ合いなども楽しむことができます。またオーストラリアはラグビー(ラグビーと言ってもワラビーズのような15人制ではなく13人制でした)が盛んで先生方の朝の会話は前日に地元チームの試合の結果から始まっていました。我々も地元のラグビー場で試合を観戦する機会がありましたがすごい熱気で、まるで甲子園球場での阪神タイガースの試合を観戦しているような雰囲気でした。
ハワイと同じく、オーストラリアも相互訪問を実施していて隔年でオーストラリアの子どもたちも日本を訪問します。オーストラリアの子どもたちの印象をホームステイ先の保護者の方に聞いてみると「子どもたちは真面目で興味関心も強い」との声が多く聞かれました。また、訪日前に事前学習をかなり積んでくるようでいろいろと質問をしてくるそうです。さらに用意された食事(主に日本食)などは必ず全部に手をつけるようで国際交流の趣旨も教わってきているようです。(ハワイの子どもたちはイエス・ノーがはっきりしていてしたくないものはしない、食べたくないものは食べないなど自由奔放に活動していました)
日本にもたくさん誇れる文化があります。いろいろと学んで帰ってくれると嬉しいです。
「向上してきた日本の子どもたちの国際力」
オーストラリアとの交流は現在でも続いており今年も訪日したそうです。私が現場から退いて十数年経つので、国際交流の行事も変化していると思います。日本の子どもたちにしても以前に比べるとはるかに英語力が向上しています。また、日本自体も外国の方々の多くの訪日により国際感覚(外国の人と接することへの慣れ)も優れてきて観光地などでは多くの土産店や飲食店で日本人の店員さんが英語等で対応しています。電車に乗ったら英語や中国語などのアナウンスが流れてくるなど外国語に触れることが当たり前のようになってきました。いまの子どもたち(小中高生)が英語などの外国語を学ぶ目的も以前のような「大学受験のため」ではなく、外国の人々と触れ合うツールとして実際に活用するためのものになってきていると思います。(なってほしいという希望も含めて)
いまインターナショナルスクール(幼稚園・保育園の年齢)に通う子どもたちが増えていると聞きます。それだけ保護者の方々の英語に対する関心が高いということです。その関心を生かすためにも小学校の英語教育がもう一段も二段も発展することを願っています。(私も小学校現場に長く在籍していましたので小学校教育で果たさなければならない課題「人格形成」や「基礎学力」などがたくさんあることは分かった上で)
多くの私立小学校が取り組んでいる国際教育(英語などの語学教育や海外研修など)が
さらに発展し日本の小学校の国際教育の先駆けになってくれることを期待しています。
「暑い!」「暑い!」と言い続けた今年の夏も9月下旬に入り秋を感じるようになってきました。今年の夏は早くから始まり遅くまで続く長い夏でした。私は今年はじめて日傘を購入しました。いままで日傘は女性が使うものという認識で男性の自分が使うなんて考えもしませんでしたが使ってみて帽子よりはるかに涼しく快適でした。今年は男性でも日傘を使う人が増えていると聞きます。また中高生はもちろん通学に日傘を使う小学生も見かけました。今後、数年前から流行りだしたハンディファンのようにかわいいデザインや新しい機能を備えた日傘が流行るかもしれませんね。
さて、海外引率体験記も「ハワイ編」「台湾編」と続きましたが今回はオーストラリア
をご紹介します。
「オーストラリア編」
私の勤務していた小学校とオーストラリアのブリスベンにある小学校の交流が始まったのは1995年(平成7年)からです。ハワイや台湾と同じく「環太平洋計画」の一環として早くから準備を進め、初めに先生方の交流から始めました。ハワイ(約6.5時間)や台湾(3.5時間)にくらべてフライト時間が長い(約9時間)ので心配しましたが時差がほとんどない(1時間)ので実施可能と判断しました。オーストラリア訪問でもメインはホームステイです。ハワイと違いオーストラリアのご家庭は日本語を話せる方は皆無に近く、さらに1家庭に1人での訪問(ハワイは2人一組)で少しハードルが高くなります。それでも毎年たくさんの希望者がいて子どもたちの勇気に感心させられたものです。行事はハワイと同じように学校訪問や歓迎行事、ホームステイなどで充実した日々を過ごします。オーストラリアのホームステイを経験した子どもたちは他の訪問先にくらべても英語や異国文化への関心が高くなって帰ってきたように感じました。ブリスベンはビジネス街なので派手な観光地はありませんが、豊かな自然と動物(コアラなど)との触れ合いなども楽しむことができます。またオーストラリアはラグビー(ラグビーと言ってもワラビーズのような15人制ではなく13人制でした)が盛んで先生方の朝の会話は前日に地元チームの試合の結果から始まっていました。我々も地元のラグビー場で試合を観戦する機会がありましたがすごい熱気で、まるで甲子園球場での阪神タイガースの試合を観戦しているような雰囲気でした。
ハワイと同じく、オーストラリアも相互訪問を実施していて隔年でオーストラリアの子どもたちも日本を訪問します。オーストラリアの子どもたちの印象をホームステイ先の保護者の方に聞いてみると「子どもたちは真面目で興味関心も強い」との声が多く聞かれました。また、訪日前に事前学習をかなり積んでくるようでいろいろと質問をしてくるそうです。さらに用意された食事(主に日本食)などは必ず全部に手をつけるようで国際交流の趣旨も教わってきているようです。(ハワイの子どもたちはイエス・ノーがはっきりしていてしたくないものはしない、食べたくないものは食べないなど自由奔放に活動していました)
日本にもたくさん誇れる文化があります。いろいろと学んで帰ってくれると嬉しいです。
「向上してきた日本の子どもたちの国際力」
オーストラリアとの交流は現在でも続いており今年も訪日したそうです。私が現場から退いて十数年経つので、国際交流の行事も変化していると思います。日本の子どもたちにしても以前に比べるとはるかに英語力が向上しています。また、日本自体も外国の方々の多くの訪日により国際感覚(外国の人と接することへの慣れ)も優れてきて観光地などでは多くの土産店や飲食店で日本人の店員さんが英語等で対応しています。電車に乗ったら英語や中国語などのアナウンスが流れてくるなど外国語に触れることが当たり前のようになってきました。いまの子どもたち(小中高生)が英語などの外国語を学ぶ目的も以前のような「大学受験のため」ではなく、外国の人々と触れ合うツールとして実際に活用するためのものになってきていると思います。(なってほしいという希望も含めて)
いまインターナショナルスクール(幼稚園・保育園の年齢)に通う子どもたちが増えていると聞きます。それだけ保護者の方々の英語に対する関心が高いということです。その関心を生かすためにも小学校の英語教育がもう一段も二段も発展することを願っています。(私も小学校現場に長く在籍していましたので小学校教育で果たさなければならない課題「人格形成」や「基礎学力」などがたくさんあることは分かった上で)
多くの私立小学校が取り組んでいる国際教育(英語などの語学教育や海外研修など)が
さらに発展し日本の小学校の国際教育の先駆けになってくれることを期待しています。
The following two tabs change content below.


上席顧問 津田克彦
元私立小学校校長、元大阪府私立小学校連合会会長。
プラチナム学習会では保護者相談、進学指導、及び、「小学校受験対策集団コース」を担当。元私立小学校校長の長年の経験を活かした、噂に左右されない本質的な指導で万全の準備を進めます。特に小学校入学後に後伸びできる子ども達の指導に努めています。
最新記事 by 上席顧問 津田克彦 (全て見る)
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(8) 2025.11.10 - 2025/11/10
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(7) 2025.9.30 - 2025/09/30
- 新コラムⅡ 津田克彦の「個人の意見です!」(6) 2025.7.25 「海外引率体験記(第5回)」 - 2025/07/25